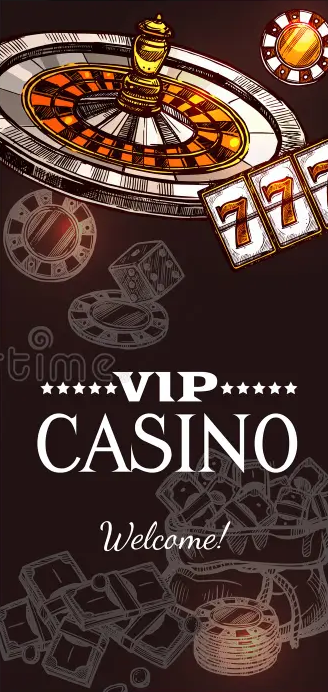シナプスの可塑性(かそせい) 高校生物
YOUR LINK HERE:
http://youtube.com/watch?v=3Rn8SMPel44
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】 • シナプスの可塑性(シナプス可塑性)について解説します。 • *すみません。この動画では「シナプスの可塑性」と言っていますが、今の高校教科書、資料集は「シナプス可塑性」という語を使っています(神経科学では、単に「可塑性plasticity」と言うこともあります)。いずれも「synaptic plasticity」を表す語であり、同義ですが、高校生は今使っている教科書、資料集の語を使いましょう。 • ●「可塑性(かそせい)」とは、一般に、生体が外界から何らかの信号に対応し、正常状態を保持するのに示される変化的な性質を指す。神経科学においては、可塑性は、何らかの原因によりシナプスでの伝達効率に変化が起こる性質を指す(粘土に指を押し込むと、粘土の形が変化したまま戻らない。可塑性は、そのように変化の情報が保たれるイメージ)。 • ●軟体動物腹足類の仲間であるアメフラシのもつ神経細胞の細胞体は、非常に大きく、直径200マイクロメートルもある(すべての動物の中でも最大級である)。さらに、中枢神経系は2万個程度のニューロンしかなく、研究しやすい。エリック・カンデルはこのアメフラシの持つ巨大なニューロンを用いて研究を行い、2000年にノーベル賞を受賞した。 • 余談の余談だが、この受賞は日本ではあまり騒がれなかったらしい。無脊椎動物の神経科学が軽視されているとしたら、悲しい話である。研究費は事実削られている。 • 問題:シナプス間隙に分泌される伝達のための物質を総称して何というか。 • 答え:神経伝達物質 • 問題:神経細胞内部(正確には神経終末)に多数存在する、神経伝達物質を含む小胞を何というか。 • 答え:シナプス小胞 • *今回は高校教科書に合わせて説明した。正確には以下のような反応が起こる。 • セロトニンは、静止状態で活性化しているカリウムチャネルの一種を閉じさせることで静止膜電位を上昇させ、電位依存性カルシウムチャネルを開口を促進する。さらに、セロトニンは、電位依存性カリウムチャネルも不活性化し、活動電位の時間幅を拡大して、活動電位1発あたりの神経伝達物質の放出を増幅する。いずれにしろ、このようなアメフラシの短期記憶(促通)は、『イオンチャネルの修飾』によっておこる。新たなタンパク質合成を必要としないので、秒から分のスケールという非常に短い時間で起こる現象である。 • ●アメフラシの慣れ、脱慣れ、鋭敏化についても、資料集で復習しておきましょう。 • *『慣れ』 • ・・・特定の反射を引き起こす刺激を反復して提示すると、次第に反射が減弱していく現象。アメフラシのえら引っ込め反射(えら引き込み反射)についての慣れが教科書では扱われることが多い(水管に対して接触刺激を与えると、アメフラシは防御のためにエラと水管を体の中に引き込む。ちなみに、水管は、海水や排出物を吐き出す噴出口である)。 • アメフラシの場合、水管刺激を繰り返した後のえらの引き込み量の減少(慣れ)は、感覚ニューロンと運動ニューロンの伝達効率の低下(感覚ニューロンから放出される神経伝達物質の総量が減少する)が原因であると考えられている。 • このようなシナプスの伝達効率の抑制による「慣れ」は、ザリガニの逃避反応など、動物界に広く見られる。 • *『脱慣れ』と『鋭敏化』 • ・・・動物は、有害な刺激によって、恐怖を学習し、有害な刺激だけではなく、同時に起こった他の有害でない刺激に対しても活発に反応するようになるのが普通である。その結果、えら引っ込め反射などの防御反射は増強される。 • えら引っ込め反射についての慣れが成立したアメフラシの尾部に電気ショックを与えると、えら引っ込め反射が回復する。これを『脱慣れ』という。 • さらに強い電気ショックを与えると、弱い水管刺激に対しても敏感に(普通よりも敏感に)反射が起こるようになる(えらの引き込み量は劇的に大きくなる)。これを『鋭敏化』という。 • ●慣れ、脱慣れ、鋭敏化の現象は、シナプスでの伝達効率の変化が関わる(慣れはシナプス伝達効率の抑制によって、鋭敏化はシナプス伝達効率の増強によって起こる)。シナプスでの伝達効率が変化することをシナプス可塑性(かそせい)という。 • *今回の動画は、脱慣れや鋭敏化の背景について解説している。 • ●この動画で解説したような鋭敏化は、通常1時間以内にもとにもどってしまう。このような鋭敏化を短期の鋭敏化という。対して、長期の鋭敏化では、新規タンパク質の合成が関わり、シナプスの数が増加する。 • ●以下に長期の鋭敏化の流れを記す。 • ①繰り返しの刺激によって、細胞内のcAMP濃度が強く、長期間上昇する。 • ②cAMP依存性プロテインキナーゼ(PKA)が核内に移行する(正確には、PKAの触媒サブユニットが核内に入る)。 • ③PKAは、いろいろな遺伝子の発現に影響を与える(PKAは、転写因子CREBのような核内の基質をリン酸化し、新たな遺伝子発現を引き起こす)。 • ④新しいシナプスが形成される。 • *この長期の鋭敏化は1日以上持続する(短期の鋭敏化は、1時間以内に元に戻ってしまう)。さらに数日にわたり訓練を続けると、1週間以上続く鋭敏化を引き起こす。 • *この仕組みは、反復された経験により、短期記憶が長期記憶へと変換するしくみに通じていると考えられている。 • (以上の変化の他、長期の鋭敏化でも、短期の鋭敏化のように、感覚ニューロンと運動ニューロンのシナプスを含むいくつかのシナプスの伝達効率の変化が起こることが知られている。) • noteに簡単なイラストがある。 • https://note.com/yaguchihappy/n/nedf4... • • • #神経 • #高校生物 • #シナプス
#############################

 Youtor
Youtor