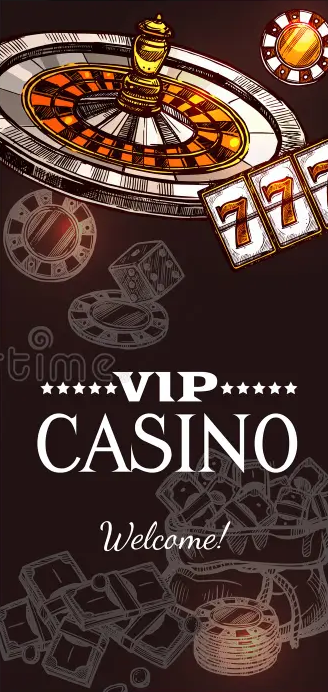細胞性免疫 高校生物基礎
YOUR LINK HERE:
http://youtube.com/watch?v=pS4eK26aLk8
【 note : https://note.com/yaguchihappy 】 • 細胞性免疫、キラーT細胞について講義します。 • 語呂「キラキラで小さい(キラーT細胞が関わる細胞性免疫)」小さいの、ちい、でTと読む。無理矢理ですね。 • • ●細胞性免疫では、キラーT細胞が、直接ウイルス感染細胞などを殺傷する。 • ①樹状細胞が食作用で抗原を取り込み、ヘルパーT細胞とキラーT細胞に抗原提示を行う。 • ②ヘルパーT細胞がキラーT細胞を活性化させる。 • ③キラーT細胞が抗原に感染した細胞を直接殺傷する(ヘルパーT細胞はマクロファージなどの食細胞を活性化させる)。 • ●抗体から、細胞内に潜伏して逃れる細菌やウイルスがいる。結核菌などは、マクロファージに食べられた後でさえ、そのマクロファージの細胞内で生存する。そのような場合、細胞ごと潰してしまう細胞性免疫が役に立つ。 • ●ヘルパーT細胞はマクロファージなどの食細胞を活性化させる物質を分泌する。もともと「細胞」性免疫とは、食「細胞」を活性化させる免疫として知られていた。 • ●細胞が分泌して、自分の近くにいる他の細胞に働きかけるような物質を総称してサイトカインという。特に白血球が分泌するサイトカインをインターロイキン(白血球=ロイコサイトleukocyte。インターロイキンinterleukinは、「白血球間の相互作用に働く生理活性物質」という意味の造語)という。 • ●T細胞は、骨髄にある造血幹細胞から未熟な状態で生じ(骨組織に守られる骨髄は造血組織である。つまり骨髄は血球産生の場である)、胸腺Thymusへ移動して成熟(分化)することが知られている(対して、B細胞は骨髄で分化し、そのまま骨髄内でおおよそ成熟する)。また、T細胞受容体はMHC分子と結合した抗原ペプチドを認識するが、抗原分子あるいは抗原ペプチドそのものとは直接結合できない(対して、B細胞は、抗原と直接結合できる受容体をもつ)。 • ●インフルエンザが毎年流行るのはなぜだろう?実はインフルエンザは点突然変異を繰り返している。さらに、異なるタイプのインフルエンザ同士でRNA遺伝子組換えが起こる場合がある。この場合は大流行になることがある(『新型インフルエンザ』は、新しくヒトの世界で感染するようになったものを指すこともあるが、多くは行政的な用語として使われており、生物学的定義は明確でない)。 • 問題:細胞性免疫において、ウイルス感染細胞などを殺傷する細胞を答えよ。 • 答え:キラーT細胞 • 問題:胸腺を切除したマウスでは、移植された組織に対する拒絶反応の程度が低下することが知られている。胸腺はT細胞が成熟する場所である。このことからいえることは何か。1つ選べ。 • ①拒絶反応にはT細胞が関わる。 • ②拒絶反応にT細胞は関与しない。 • ③拒絶反応を起こすために胸腺は必要ない。 • 答え:① • ●かつて、体を守る仕組みには「体液」が関わるとする体液説と、「細胞」によるとする細胞説が対立していた。北里柴三郎による血清学の発展によって細胞説の影は一時薄くなったが、現代では、「体液性免疫」と「細胞性免疫」という2つの仕組みが存在することが明らかになっている。体液説と細胞説はどちらも正しかったのである。 • *北里柴三郎:破傷風菌の発見者。ジフテリアおよび破傷風抗毒素血清の発見者。慶応義塾大学医学部、日本医師会を設立し、初代医師会長となった。門下に志賀潔がある。 • *志賀潔:赤痢菌を発見。赤痢菌属(シゲラ属 )Shigella は、志賀潔を称えて命名された。 • *ジフテリア菌、破傷風菌、赤痢菌はすべて細菌(ジフテリア菌はコリネバクテリウム属、破傷風菌はクロストリジウム属)。 • • #恒常性 • #生物基礎 • #細胞性免疫
#############################

 Youtor
Youtor